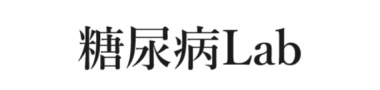糖尿病によるしびれを感じていませんか?手足がジンジンする、ピリピリと痛む、感覚が鈍くなってきた――そんな感覚は、単なる疲労ではなく糖尿病に伴う神経障害の初期サインかもしれません。放置すれば、重大な合併症につながる恐れもあります。本記事では、糖尿病が原因で起こる「しびれ」の正体や見分け方、早期対応の重要性、そして今すぐできる対処法について、信頼できる情報に基づいてわかりやすく解説します。
糖尿病によるしびれとは?その原因とメカニズム
糖尿病によって引き起こされるしびれの多くは、「糖尿病性神経障害」と呼ばれる合併症によるものです。糖尿病が長く続くことで、高血糖が末梢神経に悪影響を与え、しびれや感覚異常、痛みなどの症状を引き起こします。神経は全身に張り巡らされているため、足や手、指先などあらゆる部位に影響を及ぼします。
なぜ糖尿病でしびれが起きるのか?
高血糖状態が続くと、神経細胞に栄養や酸素を運ぶ毛細血管が障害を受けます。その結果、神経がダメージを受けやすくなり、末梢神経の機能が低下してしまうのです。これが「しびれ」や「痛み」「鈍さ」などの感覚異常として現れます。
糖尿病によるしびれの特徴とよく出る部位
糖尿病によるしびれは、ほかの病気や単なる疲労からくるしびれとは異なる特徴があります。どこに、どんなふうに出るのかを把握しておくことが、早期発見・対処につながります。
1. 足の指・裏・ふくらはぎなど末端から始まる
糖尿病性神経障害では、しびれはまず足の指や裏側など、末端から始まることが多いとされています。これは「手袋・靴下型」とも呼ばれ、左右対称に広がっていくのが特徴です。
2. ピリピリ・ジンジンとした痛みを伴うことも
感覚が鈍くなるだけでなく、ピリピリとした電気が走るような痛み、ジンジンとした鈍痛が現れることもあります。夜間や休息中に強く感じることが多く、睡眠障害の原因にもなります。
3. 手の指・手のひらにも拡がることがある
進行すると手の指やひら、腕までしびれが広がることがあります。日常生活の中で細かい作業がしづらくなったり、握力の低下を感じるケースもあります。
しびれ以外にもある糖尿病性神経障害の症状
糖尿病による神経障害は「しびれ」だけではありません。神経には感覚をつかさどる「感覚神経」、内臓の働きを調整する「自律神経」、筋肉の動きをコントロールする「運動神経」などがあり、それぞれに異なる症状が現れます。
感覚鈍麻(感覚が鈍くなる)
しびれが進行すると、熱さや痛みなどの刺激に鈍くなり、やけどやけがに気づかず悪化することもあります。特に足の裏は異常に気づきにくいため、注意が必要です。
冷えや焼けるような痛み
神経が誤作動を起こすことで、実際には冷えていないのに「冷たい」と感じたり、何もしていないのに「焼けるような痛み」を覚えることがあります。
自律神経の異常
胃の不調(胃もたれ・食欲不振)、立ちくらみ、異常発汗、便秘や下痢の繰り返しなどがみられることがあります。これは内臓や血圧の調整を担う自律神経の障害によるものです。
糖尿病のしびれで病院に行くべきタイミングとは?
糖尿病が原因かどうかを見極めるには、医療機関での診断が不可欠です。以下のような症状があれば、なるべく早めに受診を検討しましょう。
病院に行くべきチェックポイント
- 足や手の先がジンジン・ピリピリとしびれる
- 感覚が鈍く、熱さや痛みに気づきにくい
- 歩いていても足裏の感覚がない
- 一部だけでなく広範囲にしびれが拡がってきた
- 夜間、しびれや痛みで眠れない
糖尿病のしびれに対する5つの対策
糖尿病によるしびれは、完全に元に戻すことは難しいものの、進行を食い止めたり、軽減することは可能です。ここでは、日常生活で取り組める5つの対策をご紹介します。
1. 血糖コントロールを最優先に
神経障害の進行を防ぐには、まず血糖値を適切な範囲で安定させることが最重要です。医師の指導に従って、食事・運動・薬物療法を継続しましょう。
2. 足の保温と血流促進
足先の血行をよくすることで、しびれの悪化を防ぐことができます。冷えやすい方は、靴下や湯たんぽなどを使って適度な保温を意識しましょう。
3. フットケアを日課にする
糖尿病の方は足にけがをしても気づきにくく、感染や壊疽のリスクが高まります。毎日、足を洗って清潔にし、傷や変色がないか確認する習慣をつけましょう。
4. ビタミンB群を意識した食事
ビタミンB1・B6・B12などは神経の働きを保つ栄養素です。豚肉、大豆、魚、卵などに多く含まれており、日々の食事でバランスよく摂取することが大切です。
5. 定期的な検診と神経機能のチェック
しびれの進行を見逃さないためにも、内科や糖尿病専門医での定期検査は欠かせません。問診だけでなく、神経伝導速度や血流検査を行うことで、状態を客観的に把握できます。
信頼できる公的情報を参考にしよう
糖尿病と神経障害に関する正しい知識を得るためには、信頼できる公的機関の情報を活用することが重要です。以下のサイトでは、最新かつ正確な医学情報が提供されています。
まとめ
糖尿病のしびれは、神経障害という深刻な合併症の初期サインである可能性があります。足先のジンジンとした感覚やピリピリした痛みを「よくあること」と軽視せず、早めに医療機関での診断を受けることが大切です。また、日々の血糖コントロールやフットケア、適切な栄養摂取を継続することで、症状の悪化を防ぎ、安心して生活を送ることが可能になります。