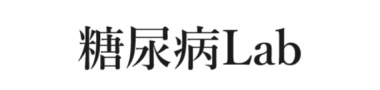年々増加している「糖尿病」。
一度発症してしまうと、完治が難しく、さまざまな合併症を引き起こす恐ろしい病気です。
しかし、糖尿病は早めに原因を知り、対策を取ることで予防できることもまた事実。
本記事では、厚生労働省や日本糖尿病学会など信頼できる情報をもとに、糖尿病の主な原因ランキングTOP10をわかりやすくまとめました。
「血糖値が高め」と言われたことがある方、家族に糖尿病の方がいる方は必見です。
記事を読み進めることで、今日から実践できる血糖値対策もご紹介しています。
自分自身や大切な家族を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
糖尿病の原因ランキングTOP10
糖尿病は、年齢に関係なく誰にでも起こりうる重大な生活習慣病です。
一見、遺伝的な要素が強いように思われがちですが、実際には生活習慣や日常のちょっとした行動の積み重ねが大きく影響しています。
この記事では、厚生労働省「e-ヘルスネット」、日本糖尿病学会、メディカルノートなどの信頼できる情報をもとに、糖尿病の主な原因をランキング形式で解説します。
「糖尿病 原因」をしっかり理解し、日々の生活を見直すヒントにしていただければ幸いです。
第10位 ストレス(慢性的なストレス)
ストレスが慢性的に続くと、自律神経のバランスが崩れ、血糖値を上げるホルモンであるコルチゾールの分泌が増加します。
この状態が長期間続くと、体内のインスリン抵抗性が高まり、血糖コントロールが難しくなります。
また、ストレスによる過食や運動不足も、間接的に糖尿病のリスクを高めます。
日常的にストレスケアを意識し、リラックスする時間を持つことが、糖尿病を未然に防ぐ大切な対策です。
第9位 高脂肪・高カロリーな食生活
ファストフードや脂っこい食事を続けていると、体脂肪、特に内臓脂肪が蓄積し、インスリンの効きが悪くなります。
さらに高カロリーな食生活は、血糖値スパイク(食後血糖値の急上昇)を引き起こし、膵臓に過度な負担をかけ続けます。
この負荷が蓄積することで、インスリン分泌機能が低下し、結果として糖尿病を招くリスクが高まるのです。
野菜中心の食事、低カロリー高たんぱくのメニューを意識することが、糖尿病予防には欠かせません。
第8位 睡眠不足
睡眠不足は、血糖値コントロールに悪影響を与えることが近年の研究で明らかになっています。
寝不足になると、インスリン感受性が低下し、血糖値を下げる力が弱まります。
また、睡眠不足は食欲を増進させるホルモン(グレリン)を増加させ、暴飲暴食を誘発しやすくなります。
規則正しい睡眠を確保し、質の高い休息を取ることは、糖尿病リスクを下げる大切なセルフケアです。
第7位 運動不足
運動は、血糖をエネルギーとして消費する最大の手段です。
運動不足が続くと、筋肉量が減少し、インスリンの効きが悪くなり、血糖値が上がりやすい体質に変わってしまいます。
さらに運動不足は肥満を招き、糖尿病リスクを二重に高める要因となります。
ウォーキングや軽い筋トレなど、毎日の生活に無理なく運動を取り入れることが、血糖コントロールには非常に重要です。
第6位 加齢
加齢に伴い、膵臓のβ細胞(インスリンを分泌する細胞)の機能が徐々に低下します。
また、筋肉量も減少しやすくなるため、基礎代謝が落ち、血糖値が上がりやすい体質へと変わっていきます。
特に40歳以降は、生活習慣の見直しと、定期的な健康診断による血糖チェックが必要不可欠です。
「年齢だから仕方ない」と放置せず、予防のために積極的な対策を講じることが大切です。
第5位 内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)
見た目にはそれほど太っていなくても、お腹周りに脂肪が集中している場合は注意が必要です。
内臓脂肪は、インスリンの作用を阻害する物質を分泌し、血糖コントロールを悪化させることがわかっています。
特に男性や更年期後の女性に多く見られ、放置すると糖尿病、高血圧、脂質異常症などの「死の四重奏」に繋がる危険があります。
ウエスト周りを意識し、早期に生活改善を図ることが重要です。
第4位 不規則な食生活(早食い・間食・夜食)
食事の時間帯や食べ方が不規則になると、血糖値の急激な上下動(血糖値スパイク)が起こりやすくなります。
特に「夜遅い食事」「早食い」「間食が多い」といった習慣は、膵臓に過剰な負担をかけ、インスリン分泌機能を低下させます。
さらに、夜間は体のエネルギー消費が低下するため、夜食で摂取したカロリーは脂肪として蓄積されやすくなり、内臓脂肪型肥満へと直結します。
規則正しい食事リズムを守り、ゆっくり噛んで食べることを意識することが、糖尿病の予防には欠かせません。
第3位 高血圧・脂質異常症など他の生活習慣病
糖尿病は単独で発症することもありますが、高血圧や脂質異常症(高コレステロール血症)と同時に起こるケースが非常に多いです。
これらの生活習慣病が重なることで、血管への負担が何倍にも増大し、動脈硬化が加速、心筋梗塞や脳卒中のリスクが跳ね上がります。
特に脂質異常症では、血中の悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が増加し、インスリンの作用を妨げ、結果として糖尿病を悪化させる悪循環に陥ります。
生活習慣病はすべて「つながっている」ことを意識し、早期から多角的な対策を行うことが重要です。
第2位 遺伝・家族歴
親や兄弟姉妹に糖尿病患者がいる場合、自身が糖尿病を発症するリスクは一般人の2~3倍に跳ね上がります。
これは、インスリン分泌能力やインスリン感受性に関わる遺伝的な要因が影響しているためです。
しかし、遺伝があっても必ず発症するわけではありません。
適切な生活習慣を心がけることで、糖尿病の発症リスクを大幅に低減できることもわかっています。
家族歴がある場合こそ、日頃から血糖値に対する意識を高め、予防に努めることが大切です。
第1位 肥満(特にBMI25以上)
糖尿病発症の最大のリスクファクターは、やはり「肥満」です。
特に内臓脂肪が蓄積した状態では、インスリン抵抗性が強くなり、体がインスリンの指示に反応しにくくなります。
さらに肥満によって慢性炎症状態が持続し、血糖コントロールがますます困難になります。
BMI(体格指数)が25を超えている場合は、糖尿病発症リスクが劇的に高まるため、減量が最重要の課題となります。
適正体重を目指し、無理のない範囲でダイエットを継続することが、糖尿病予防の基本です。
糖尿病とは?血糖値との深い関係
糖尿病とは、インスリンという血糖値を下げるホルモンの作用がうまく働かず、血液中にブドウ糖が過剰にたまってしまう病気です。
特に2型糖尿病は、遺伝的素因に加え、肥満、運動不足、不規則な食生活といった生活習慣が主な原因となります。
血糖値が高い状態が続くと、血管に深刻なダメージを与え、目の網膜症、腎臓病、神経障害、心筋梗塞、脳卒中などの合併症を引き起こします。
糖尿病は進行性の病気であり、放置すれば命にかかわる重大な結果を招きます。
「血糖値が少し高め」と指摘された時点で、すぐに生活習慣を見直し、適切な対策を始めることが、健康寿命を守るために欠かせません。
血糖値を下げるために今できること
糖尿病は、発症してからではなく、発症する前からの予防と早期対策が何よりも重要です。
血糖値を下げるためには、今日からすぐに取り組める生活習慣の改善がカギとなります。
ここでは、専門機関の推奨内容をもとに、血糖コントロールに直結する具体的な行動をわかりやすく解説します。
食生活を見直す
- 野菜を最初に食べる(ベジファースト)
食物繊維は糖質の吸収を穏やかにする効果があります。食事の最初にサラダや野菜のおかずを食べる習慣をつけましょう。 - 炭水化物を摂りすぎない
白米、パン、麺類など炭水化物中心の食生活は見直し、たんぱく質や脂質もバランスよく摂ることが大切です。 - 間食と夜食を控える
血糖値の乱高下を防ぐために、規則正しい時間に3食をしっかり食べ、不要な間食はできるだけ避けましょう。
運動を日常に取り入れる
-
ウォーキングを毎日の習慣に
1日20~30分のウォーキングでも、血糖値を下げる効果が期待できます。なるべく毎日、無理のない範囲で体を動かしましょう。 -
筋トレもおすすめ
筋肉量が増えると、インスリンの働きが改善され、血糖コントロールがしやすくなります。
スクワットや腕立て伏せなど、自宅でできる軽い筋トレから始めてみましょう。
ストレスを減らし、睡眠の質を高める
-
リラックスできる時間を持つ
趣味や瞑想、アロマ、軽いストレッチなど、自分に合ったリラックス法を見つけてストレスを溜め込まないことが大切です。 -
睡眠をしっかり取る
睡眠不足は血糖コントロールを悪化させます。1日7時間程度を目安に、質の良い睡眠を確保しましょう。
血糖値の変動を「見える化」する
血糖値管理ツールを活用する
自分の血糖値の変動をリアルタイムで知ることが、食事や運動の改善につながります。
自分の体と向き合うためにも、血糖測定ツールを積極的に取り入れましょう。
糖尿病は原因を知り早めに対策することが重要【実体験を踏まえて】
筆者自身も、かつて健康診断で「血糖値が高め」と指摘されながら、病院への受診を後回しにしてしまいました。
その結果、糖尿病が進行し、血管がもろくなり、脳底動脈解離という重篤な血管障害を起こし、脳梗塞を発症。
救急搬送時のHbA1cは驚きの13超(正常値は5.5%未満)。
左半身が動きにくくなり、言葉もうまく話せない後遺症を負うことになりました。
一歩間違えれば命を落としていたかもしれません。
この経験から強く感じたことは、
「血糖値が高め」とわかったその時から、すぐに行動を起こすべきだということです。
糖尿病は、初期には自覚症状が乏しいため、油断してしまいがちです。
しかし放置すれば、体の中で静かに、しかし確実に進行していきます。
あなた自身や、大切な人の未来を守るためにも、
「糖尿病の原因」を正しく理解し、早めに対策を始めることが何よりも大切です。
血糖値の管理をもっと手軽にするには?
血糖値コントロールに本気で取り組むなら、
「自分の血糖値の動きをリアルタイムで把握する」ことが非常に効果的です。
【フリースタイルリブレ2】なら
-
腕に小型センサーを貼るだけで、血糖値をリアルタイム測定
-
スマホアプリと連携し、食事や運動の影響がすぐに「見える化」
-
血糖値の急上昇・急下降を防ぐためのヒントがわかる
フリースタイルリブレを使うことで、何を食べれば、血糖値がどのくらい上がるのか、血糖値が上がり過ぎたから運動で下げよう、今、食べるのはやめようなどの対策をすることができます。
忙しい毎日の中でも、無理なく、そして確実に血糖値コントロールを実践できる強力な味方です。
特にフリースタイルリブレ2なら自動で血糖値を記録してくれ、スマートフォンで確認することができます。是非、確認されてみて下さい。
▶フリースタイルリブレ(FreeStyleリブレ)とは? (詳細を説明しています)