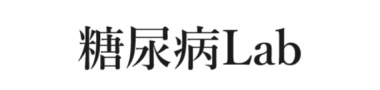糖尿病と合併症は、切っても切れない深い関係にあります。実際、糖尿病そのものよりも合併症による健康被害の方が深刻であり、視力の低下・腎機能障害・神経障害など、生活の質を大きく下げる可能性があります。
特に怖いのは、合併症の多くが「ある程度進行するまで自覚症状がない」ということ。そのため、気づいたときには治療が難しい段階に入っているケースも少なくありません。
この記事では、糖尿病で起こりやすい代表的な7つの合併症を丁寧に解説するとともに、早期発見・予防のためのポイントも紹介していきます。
※本記事は一般的な医療情報をもとに構成されています。治療の判断は必ず主治医と相談の上、行ってください。
糖尿病と合併症の基本知識
糖尿病は、慢性的に血糖値が高い状態(高血糖)が続く病気です。この高血糖が長期間続くことで、全身の血管がじわじわと傷ついていき、さまざまな合併症を引き起こします。
特にダメージを受けやすいのが、血液を運ぶ「血管」です。合併症は、以下の2つに大きく分類されます:
- 細小血管障害(ミクロ血管障害):毛細血管が傷つくことで起きる障害。代表例は「網膜症」「腎症」「神経障害」
- 大血管障害(マクロ血管障害):太い血管(動脈など)が硬化・狭窄・破裂することで起こる「脳梗塞」「心筋梗塞」など
合併症は「放置」によって静かに進行する
糖尿病の初期には、ほとんど自覚症状がありません。合併症が発症するまで無症状のまま年月が経過することも多く、気づいたときには失明寸前、あるいは腎臓がほとんど機能しなくなっていたという例も少なくありません。
しかし、これは「糖尿病が怖い病気だから」というよりも、きちんと管理していないから起こる結果です。合併症のリスクは、血糖値・血圧・脂質の管理、そして定期検査によって大きく下げることが可能です。
代表的な合併症7選とその症状
糖尿病が原因で起こる合併症は多岐にわたります。ここでは特に注意すべき7つの主要な合併症について、それぞれの特徴と症状を詳しく紹介します。
1. 糖尿病網膜症(視力低下・失明のリスク)
糖尿病網膜症は、眼の奥にある網膜の毛細血管が損傷して起こる合併症です。初期は無症状のことが多いですが、進行すると視野のゆがみ・視力低下・失明のリスクもあります。
国内では、中途失明の原因第1位であり、発見が遅れると不可逆的です。年に1回の眼底検査が早期発見のカギです。
2. 糖尿病腎症(腎機能の低下・透析の原因1位)
糖尿病腎症は、腎臓の毛細血管が傷ついて尿たんぱく・むくみ・血圧上昇などを引き起こす合併症です。進行すると腎機能が低下し、人工透析が必要になることもあります。
日本における透析導入の原因の約40%がこの腎症です。年1回の尿検査(アルブミン尿検査)で早期発見が可能です。
3. 糖尿病神経障害(手足のしびれ・自律神経の異常)
末梢神経障害により、手足の先にしびれ・感覚の鈍化・異常な痛みが現れます。また、自律神経が影響を受けると、立ちくらみ・発汗異常・消化不良・勃起障害などが見られます。
進行すると足の傷に気づかず感染を起こすなど、足病変のリスクも高まります。定期的な足チェックと問診が重要です。
4. 動脈硬化(脳梗塞・心筋梗塞のリスク)
高血糖は血管の内側を傷つけ、動脈硬化(血管の老化)を早めます。その結果、脳梗塞・心筋梗塞・狭心症など、命に関わる疾患のリスクが高まります。
血糖管理に加えて、血圧・コレステロール・禁煙などの生活習慣改善が不可欠です。
5. 歯周病・口腔内感染
糖尿病は免疫力の低下や血流の悪化により、歯周病や口内炎・カンジダ症などの口腔内トラブルが起こりやすくなります。
歯周病は血糖コントロールを悪化させる「相互作用」もあるため、定期的な歯科受診が重要です。
6. 足病変(壊疽・切断のリスク)
神経障害によって痛みに気づかず、血流障害で傷の治りが遅れると、足の潰瘍や壊疽(えそ)に進行し、最悪の場合は切断に至るケースもあります。
日々のセルフチェック(足の裏・指の間・靴ずれ)や、足に合った靴選びが大切です。
7. 認知症(血管性・アルツハイマー型とも関連)
糖尿病は認知症のリスク因子であることが明らかになっています。脳血管障害による「血管性認知症」だけでなく、インスリン抵抗性や炎症による「アルツハイマー型認知症」への影響も指摘されています。
食事・運動・睡眠・血糖管理の総合的な生活改善が、脳機能の維持にもつながります。
合併症を防ぐための3つの柱
糖尿病と合併症の関係は密接ですが、正しい知識と生活習慣を持てば、多くの合併症は予防または進行を遅らせることが可能です。
ここでは、糖尿病の合併症を防ぐために必要な3つの予防の柱を解説します。
1. 血糖・血圧・脂質のコントロール
糖尿病治療の基本である血糖値の適切なコントロールはもちろん、血圧と血中脂質(LDL・中性脂肪)も一緒に管理することが重要です。これらは合併症の進行に直結する因子であり、3つをセットで見ることが推奨されています。
目安となる指標は以下の通りです(※個別の目標は主治医とご相談ください):
- HbA1c:7.0%未満(または医師の指示範囲)
- 血圧:130/80mmHg未満
- LDLコレステロール:100mg/dL未満(冠動脈疾患の有無で異なる)
2. 定期的な検査と専門医の受診
合併症は初期症状がほぼないため、定期検査が唯一の早期発見手段です。以下の検査は特に重要です:
- 眼底検査(年1回以上)
- 尿検査(アルブミン尿、年1回)
- 神経機能検査(振動覚、足チェック)
- 心電図・血液脂質検査(年1回)
また、糖尿病専門医、眼科医、腎臓内科、歯科などの連携を持ち、チーム医療の活用も有効です。
3. 医師・栄養士・薬剤師との継続的な連携
糖尿病の合併症予防には、本人の努力だけでなく、医療チームとの継続的な対話が大きな意味を持ちます。血糖コントロールの状況、生活習慣、食事の偏り、服薬の正確性など、日々のちょっとした改善が合併症の回避に直結します。
かかりつけ医・管理栄養士・薬剤師・看護師など、各専門職と一緒に、自分に合ったケアプランを立てることが合併症予防の近道です。
Q&A|糖尿病と合併症に関するよくある質問
- Q糖尿病の合併症はいつから起こりますか?
- A
個人差はありますが、血糖値の高い状態が数年にわたり続いた場合に合併症が現れることが多いです。特に無自覚のまま放置された場合、発症のリスクが高まります。
- Q血糖値が少し高いだけでも合併症は起こりますか?
- A
はい。わずかな血糖上昇でも年単位で続けば血管にダメージが蓄積され、合併症のリスクが高まります。予防の観点からも早期からのコントロールが重要です。
- Q合併症の症状はどのようなものがありますか?
- A
視力低下、手足のしびれ、むくみ、立ちくらみ、口の乾き、感染症の頻発などが挙げられます。ただし初期は自覚症状がないことが多く、検査で初めて発見される場合も多いです。
- Q合併症を完全に防ぐことはできますか?
- A
100%防ぐことは難しい場合もありますが、日々の血糖・血圧・脂質管理や定期検査によって、発症を防いだり重症化を防いだりすることは十分に可能です。
信頼できる情報源【外部リンク】
糖尿病と合併症に関する正確で最新の情報は、以下の公的機関のサイトから確認できます。ご自身やご家族の健康管理に、ぜひご活用ください。
まとめ
糖尿病と合併症は密接な関係にあり、放置すれば視力・腎臓・神経・脳・心臓など、全身に重大な影響を及ぼします。
しかし、合併症は「避けられない運命」ではありません。日々の血糖コントロール・定期的な検査・生活習慣の見直しによって、発症や進行を防ぐことは十分可能です。
不安を感じたらすぐに医師や専門スタッフと相談し、「気づいたときから始める」ことが、最善の予防策です。未来の自分を守るために、今日から一歩を踏み出しましょう。