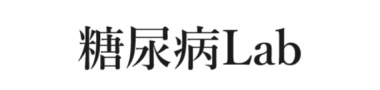糖尿病の薬について調べている方の多くは、「どんな薬を使うの?」「副作用はあるの?」といった不安や疑問を感じているのではないでしょうか。糖尿病の治療は、食事・運動などの生活習慣の改善が基本ですが、必要に応じて薬物療法(経口薬や注射薬)も行われます。症状の進行度や体質に応じて、複数の薬から選択されるのが一般的です。
本記事では、糖尿病の治療に使われる代表的な6種類の薬の特徴や副作用、選び方の考え方について、厚生労働省や日本糖尿病学会の情報に基づいて、正確かつわかりやすくまとめています。
※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の治療方針や薬の使用に関しては、必ず医師または薬剤師にご相談ください。
糖尿病の薬の基本知識
糖尿病の薬とは、血糖値を正常範囲に近づけ、合併症のリスクを減らすために用いられる治療薬の総称です。糖尿病は、インスリンの分泌不足や作用の低下によって血糖が慢性的に高くなる病気であり、進行すると腎臓障害、神経障害、網膜症など深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
薬による治療は、こうした合併症を未然に防ぐためにも重要です。とはいえ、薬を飲み始めたからといって生活習慣をおろそかにしてよいわけではありません。あくまで「食事・運動・薬」の三本柱でコントロールしていくことが求められます。
また、薬には「血糖値を下げるタイプ」「インスリンの分泌を促すタイプ」「腸での糖吸収を抑えるタイプ」などいくつかの作用機序があり、医師が患者の状態に合わせて処方を行います。
糖尿病の薬は、病気のステージや個人の体質によって使い分けが必要であり、自己判断で薬を変更・中止することは大変危険です。
糖尿病の薬の主な6種類と特徴
糖尿病の薬にはさまざまな種類があり、それぞれ作用の仕方や副作用が異なります。ここでは、日本でよく処方される6種類の薬剤について、その特徴と役割を簡潔に解説します。
1. ビグアナイド系(メトホルミン)
2型糖尿病治療の第一選択薬とされることが多く、肝臓での糖新生を抑え、筋肉や脂肪組織でのブドウ糖の取り込みを促進します。食事療法と併用して用いることで、持続的な血糖値の安定が期待されます。
代表薬:メトグルコ、グリコランなど
副作用:胃腸症状(吐き気・下痢)に注意。重度の腎障害がある方には使用できません。
2. DPP-4阻害薬
インスリンの分泌を食後に促進し、グルカゴン(血糖値を上げるホルモン)の分泌を抑える作用があります。低血糖のリスクが比較的低く、年齢に関係なく使いやすいのが特徴です。
代表薬:ジャヌビア、エクア、グラクティブなど
副作用:まれに発疹やかゆみなどのアレルギー症状、膵炎の報告もあります。
3. SGLT2阻害薬
腎臓でのブドウ糖の再吸収を阻害し、尿として体外に排出することで血糖値を下げます。体重減少や血圧低下の効果も期待でき、近年では心臓病・腎臓病予防の観点からも注目されています。
代表薬:スーグラ、フォシーガ、ジャディアンスなど
副作用:尿路感染、脱水症状、ケトアシドーシスの注意が必要です。
4. SU薬・グリニド系薬
膵臓に働きかけてインスリンの分泌を促進する薬です。SU薬は作用時間が長く、グリニド系は食後すぐの血糖上昇を抑える短時間型です。
代表薬:(SU)アマリール、オイグルコン /(グリニド)ファスティック、グルファスト
副作用:低血糖に注意。特に高齢者では注意深い管理が必要です。
5. α-グルコシダーゼ阻害薬
腸内での糖の分解と吸収を遅らせ、食後の血糖値の急激な上昇を抑えます。食事と一緒に服用する必要があります。
代表薬:ベイスン、グルコバイ、セイブルなど
副作用:おなら・腹部膨満感などの消化器症状が多いですが、重篤な副作用は少なめです。
6. GLP-1受容体作動薬(注射薬)
インスリンの分泌促進、食欲抑制、胃の動きを遅らせる作用があり、血糖値の安定と体重減少に効果が期待される注射薬です。近年では週1回の注射も登場しています。
代表薬:ビクトーザ、オゼンピック、トルリシティなど
副作用:吐き気や便秘、低血糖、稀に膵炎の報告もあり、使用時は医師とよく相談が必要です。
※薬の選択・使用は必ず医師の診断と指示に基づいて行ってください。副作用のリスクを正しく理解し、自己判断での服薬中止や変更は避けましょう。
自分に合った糖尿病の薬の選び方
糖尿病の薬は、一人ひとりの体質・生活習慣・病歴に応じて異なる薬が選ばれます。以下は、薬の選択において医師が考慮する主なポイントです。
年齢・体型・血糖値のパターン
高齢者には低血糖リスクが少ない薬が選ばれる傾向があり、肥満傾向のある方にはSGLT2阻害薬やGLP-1作動薬など体重減少効果があるものが勧められることがあります。
合併症や他の病気の有無
腎機能の低下がある方には、特定の薬が使えない場合もあります。心不全や肝機能障害などがある場合も、薬の選択肢に影響します。
ライフスタイル・継続のしやすさ
毎食ごとの内服が難しい場合は、1日1回で済む薬や、週1回の注射薬が適していることもあります。飲み忘れが多い方には、生活スタイルに合わせた工夫が求められます。
副作用と体の相性
胃腸症状やアレルギー、低血糖の出やすさなど副作用は人それぞれです。実際に薬を使いながら、医師と相談しつつ調整していくケースが多くあります。
糖尿病の薬に関するよくある疑問・誤解
糖尿病の薬について、患者さんやご家族からよく聞かれる質問をまとめました。誤解や不安を解消し、安心して治療を続ける参考になれば幸いです。
- Q糖尿病の薬は一度飲み始めたら一生続けないといけませんか?
- A
状態によっては、生活習慣の改善により薬を減らしたり、中止できることもあります。ただし自己判断せず、必ず医師と相談してください。
- Q飲み忘れた場合、あとから2回分をまとめて飲んでもいいですか?
- A
いいえ。2回分を一度に飲むと、低血糖のリスクがあります。忘れたことに気づいた時点で医師または薬剤師に相談しましょう。
- Q糖尿病の薬にはどんな副作用がありますか?
- A
薬の種類により異なりますが、低血糖、胃腸症状、アレルギー反応、膵炎などが知られています。定期的な検査と医師の診察が大切です。
- Q市販薬やサプリと併用しても大丈夫ですか?
- A
成分によっては作用を強めたり、逆に効果を妨げることがあります。市販薬や健康食品を使う前には、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
信頼できる情報源【外部リンク】
糖尿病の治療や薬に関するより詳しい情報は、以下の公的機関のサイトをご確認ください。
まとめ
糖尿病の薬は、血糖をコントロールし、合併症を防ぐために欠かせない治療のひとつです。薬の種類や作用、副作用について正しく理解することが、安心して治療を続ける第一歩になります。
生活習慣の見直しと併用して取り組むことで、薬の効果を最大限に引き出すことが可能です。疑問や不安があるときは、自己判断をせず、必ず主治医や薬剤師に相談しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の治療については必ず医療機関の指示を仰いでください。