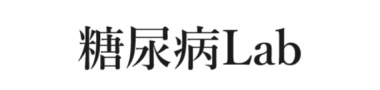糖尿病による「目のかすみ」は、見逃されやすい初期症状のひとつです。「最近視界がぼやける」「ピントが合いづらい」など、年齢や疲れのせいと思い込んでしまう人も少なくありません。しかし、放置すれば深刻な視力障害に進行する恐れもあるのです。本記事では、糖尿病によって起こる目のかすみの考えられる3つの原因と、日常生活でできる5つの対処法を、信頼できる医療情報に基づいてわかりやすく解説します。
糖尿病による目のかすみが起こる原因とは?
糖尿病は血糖値が慢性的に高くなる病気です。血糖が高い状態が続くと、全身の血管に負担がかかりますが、特に影響を受けやすいのが「毛細血管」が集まる目の内部です。眼球には網膜や水晶体、硝子体など繊細な構造があり、高血糖状態がこれらに影響を与えることで「目のかすみ」や「視力の低下」といった症状が現れるのです。
「最近、目がかすむ気がする……」「視界がぼやけるのは年のせい?」そんなふうに感じたことはありませんか?実はそれ、糖尿病のサインかもしれません。糖尿病は自覚症状が少ない“サイレントキラー”と呼ばれる病気ですが、視覚の異常は体からの重要な警告のひとつです。本記事では、糖尿病が原因で起こる「目のかすみ」のメカニズムや注意すべき症状、受診のタイミング、そして日常生活でできる目のケアまで、信頼性ある情報に基づいて詳しく解説します。
血糖値と眼球内の水分バランス
高血糖になると、血液中の浸透圧が上昇し、眼球内の水分バランスが崩れます。これにより一時的に水晶体の形が変わり、ピントが合わなくなることで「視界がぼやける」「目がかすむ」などの症状が出ることがあります。これは初期段階で見られる変化で、血糖が安定すると一時的に回復することもあります。
糖尿病による目の症状|代表的な3つの原因
糖尿病によって引き起こされる目の異常は、軽度のかすみ目だけではありません。放置することで深刻な合併症に進行することもあります。以下に代表的な3つの視覚トラブルを紹介します。
1. 一時的な視力のゆらぎ(初期)
血糖値の急激な変動があると、数日〜数週間にわたって視界がかすむ、ピントが合いづらいなどの症状が現れることがあります。これは水晶体の屈折率が変化することで起こるもので、血糖が安定すれば回復する場合もあります。ただし、頻繁に起こるようであれば注意が必要です。
2. 糖尿病性網膜症(進行性)
網膜は、目の奥にある光を感知する大切な部分です。糖尿病が進行すると、この網膜の毛細血管が破れたり詰まったりする「糖尿病性網膜症」が発生します。初期段階では自覚症状が少なく、見逃されやすいのが特徴です。進行すると視野が欠けたり、最悪の場合は失明に至ることもあります。
3. 白内障・緑内障との関連
糖尿病患者は、白内障や緑内障の発症リスクも健常者より高いことがわかっています。白内障は水晶体が濁って視界が白っぽくなる病気で、緑内障は視神経が徐々に障害を受けて視野が欠けていく病気です。どちらも放置すれば失明につながる重大な疾患です。
こんな症状があれば要注意!受診の目安
「疲れ目かな?」「年齢のせいかも」と思って放置しがちな目の違和感ですが、以下のような症状がある場合は、糖尿病による目のトラブルが疑われます。早めに眼科や内科を受診しましょう。
視界が白っぽくかすむ・にじむ
白内障や高血糖による水晶体の屈折異常の可能性があります。白っぽく見える、物がぼやけるなどの症状は初期糖尿病でも見られます。
片目だけ視力が落ちる
視力の左右差が突然出た場合は、網膜の血管トラブルや視神経の問題が考えられます。糖尿病性網膜症の初期症状である可能性も。
目の前に黒い点がちらつく(飛蚊症)
浮遊物が見える飛蚊症は、網膜剥離や硝子体出血の兆候であることも。糖尿病性網膜症が進行した結果として起こることがあります。
夜間の視力低下
暗い場所での視力が急激に落ちてきた場合、網膜の感度が低下している可能性があります。糖尿病による循環障害が関係していることもあります。
検査と診断|病院では何を調べるのか?
糖尿病が原因で目に異常が出ているかどうかを確認するには、内科と眼科の連携した検査が重要です。以下の検査を行うことで、全身と目の状態を総合的に把握できます。
血糖値・HbA1c検査
空腹時血糖値が126mg/dL以上、HbA1c(過去1〜2か月の平均血糖値)が6.5%以上で糖尿病と診断される基準になります。視覚異常の原因が糖尿病によるものかどうかの判断材料にもなります。
眼底検査・OCT(光干渉断層計)検査
眼底検査では網膜や血管の状態を直接観察できます。OCT検査では網膜の断層画像を撮影し、むくみや出血の有無、神経線維層の厚みなどが詳細にわかります。これらの検査で糖尿病性網膜症の早期発見が可能になります。
放置するとどうなる?進行リスクと失明の危険
糖尿病を原因とする目の病気は、放置すると視力低下が進行し、最悪の場合は失明に至ります。実際、日本における中途失明の原因第1位が「糖尿病性網膜症」です。進行を防ぐためには、早期の受診と血糖コントロールが必須です。
糖尿病網膜症の進行段階
糖尿病網膜症は以下の3段階で進行します。
- 単純網膜症:毛細血管の膨張や点状出血が見られるが自覚症状は少ない。
- 増殖前網膜症:血管閉塞が起こり、網膜の酸素不足が進む。
- 増殖網膜症:新生血管が発生し、破れて硝子体出血や網膜剥離を引き起こす。
治療方法とその限界
網膜症が進行した場合、レーザー光凝固術や硝子体手術、抗VEGF薬の注射などが治療に使われますが、あくまで進行を抑えるものであり、視力の完全な回復は困難です。だからこそ、早期発見と予防が最も大切なのです。
目の健康を守るためにできる生活習慣5つの対処法
糖尿病による「目のかすみ」や網膜症を防ぐには、日々の生活習慣が重要なカギになります。以下の5つの習慣は、視力の維持だけでなく、糖尿病のコントロールにも直結する行動です。
1. 血糖コントロールを最優先に
血糖値を正常に保つことが、目のトラブルを防ぐ最も基本的な対策です。食事、運動、薬物療法(必要に応じて)を継続的に行うことが重要です。
2. 栄養バランスを整える食事
野菜・たんぱく質・食物繊維をバランスよく摂取することで、血糖値の急上昇を抑え、眼の健康に必要なビタミン(特にビタミンA・C・E)も効率的に補給できます。
3. 毎日30分の軽い運動
ウォーキングや軽い筋トレなど、無理なく継続できる運動は血糖値を下げ、毛細血管の健康維持にもつながります。できれば毎日、最低でも週に3回以上を目指しましょう。
4. 定期的な眼科検診
糖尿病と診断されたら、年1回以上の眼科検診が推奨されます。自覚症状がなくても、初期の網膜症を発見できる可能性があります。
5. 目に優しい生活を意識する
スマートフォンやパソコンの見すぎは、眼精疲労や視力低下の原因になります。1時間に1回は目を休ませる、室内の照明を調整するなど、視覚環境を整える工夫をしましょう。
信頼できる情報を参考にしよう
糖尿病や目の症状について正しく理解するためには、信頼性のある情報源の活用が欠かせません。以下の公的機関のサイトでは、エビデンスに基づいた情報が掲載されています。
まとめ
「目のかすみ」は、糖尿病の症状のひとつとして現れることがあります。特に糖尿病が進行することで発症する糖尿病性網膜症は、放置すれば失明の危険性もある重大な疾患です。しかし、早期に気づいて適切に対処すれば、視力を守ることは十分可能です。日常の違和感を見逃さず、必要に応じて医師の診察を受けること。そして、生活習慣を見直し、予防と管理を徹底することが、未来の「見る力」を守る第一歩です。